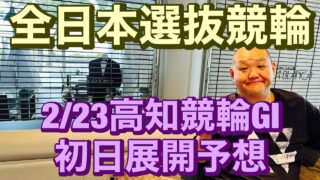 ニュース
ニュース 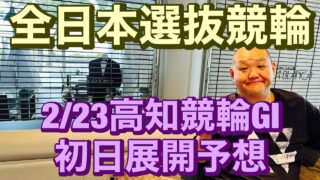 ニュース
ニュース  ニュース
ニュース 【UkuleleソロTAB譜・歌詞付き】燦燦 / 三浦大知 / ちむどんどん by Le*Retro Heart Music
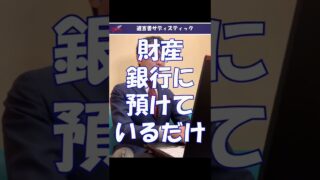 ニュース
ニュース 遺言サディスティック #歌うゆいごん司法書士 #遺言書 #ゆいごん書 #相続 #丸の内サディスティック #椎名林檎 #司法書士 #替え歌 #元バンドマン #元パチプロ #紅白に出たい
 ニュース
ニュース <3日目>第39回読売新聞社杯 #全日本選抜競輪 GⅠを生配信!2024年2月11日(日) 10時00分~16時45分 #オッズパーク #ライブ #橋本悠督 #大津尚之 #鈴木桜花 #佐々木昭彦
 ニュース
ニュース ちむどんどんする!やんばる磯!#shorts #沖縄 #磯釣り
 ニュース
ニュース 【2022年夏ドラマ】視聴率ランキング!第2話の最新速報視聴率!競争の番人 オールドルーキー 六本木クラス ユニコーンに乗って テッパチ 家庭教師のトラコ 魔法のリノベ 石子と羽男 純愛ディソナンス
 ニュース
ニュース 【NNN 読売新聞】1都3県の緊急事態宣言延長を約8割が「評価する」⁉【世論調査】
 ニュース
ニュース #燦燦 #三浦大知 朝ドラ、ちむどんどん(主題歌)最初の歌動画(4月3日投稿)があまりにも酷い出来の為申し訳なく思い、削除致しまして再アップさせていただきました🙏
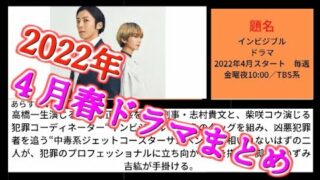 ニュース
ニュース 【ドラマ】2022年4月からスタートの春ドラマ26選!
 ニュース
ニュース